【2023年度追記】よく穂先を折る人必読!!ロッドビルダーが教える破損防止法

釣りをしていて起きるとヘコむことの筆頭とも言えるのが道具の破損。
中でも穂先を折る事故は強烈にヘコみますよね。
私のところにも
「穂先を折ってしまったけど何とかならないか?」
という相談はとても多いです。
継ぎ竿の場合だと
- 新しいティップセクションをメーカーに注文する
- 単純に折れたところにトップガイドを取り付けて使う
の二つの方法で復活させますよね。
とは言え、先ずは穂先を折らないことが最優先。
当工房のロッド、特にカワハギ、湾フグ、マルイカなどのとても繊細な穂先を持ったものは破損させてしまう方も多く、シーズンになるとご注文が一気に増えます。
これ、もちろんお仕事としてはありがたいのですが、作り手としては竿の破損ってとっても悲しいんです・・・・
特にお渡ししてすぐに折れちゃった、と言われると結構落ち込みます・・・
ですからなるべく折らないように長く使っていただきたい!!というのが偽らざる気持ちです。
そんな訳で、今回はなるべく穂先を破損させないためにはどんなことに気を付けてれば良いのか?
これについてあれこれについて考えてみます。
素材別の折れ難さ、折れやすさ
現在、船釣り用のロッドの穂先には主に以下の材料が使用されています。
- グラスソリッド
- カーボンソリッド
- メタル(形状記憶合金)
※一部にチューブラー(中空)の穂先も有りますが今回は割愛
これらはそれぞれに特徴があり、釣り竿メーカーは用途によってどんな素材を搭載するかを決定しています。(いや、していると信じたい・・・・)
材料毎に感度の違いなんかもあり、特徴について書き始めると長くなってしまいそうなので、今回はそれぞれの破損への耐性に絞って考えてみることにします。
●グラスソリッド
ガラス繊維と樹脂の組み合わせで出来ており、非常に粘りがあって、3つの中ではトータルで見ると破損には一番強い、非常にバランスの良い優秀な素材です。
とは言え、細い穂先の場合には無理な負荷が掛かったり、ちょっとした巻き込みで簡単に折れてしまいます。
●カーボンソリッド
炭素を繊維状にしたものと樹脂を組み合わた素材です。
炭素は硬度が高いので(ダイヤモンドを考えると分かりやすい)、素材自体に硬く脆い性質があります。
それを踏まえ、繊維の方向や組み合わせる樹脂の量なんかを工夫することによって粘りを出し、非常に軽くて強い材料となります。
釣竿使用時の曲げに対する強さはグラスソリッドには劣り、一ヶ所に強い負荷を掛けたり、巻き込んでしまうと簡単に折れてしまいます。
●メタル(形状記憶合金)
近年使われるようになった金属の材料です。
材質自体は金属が故に重いです。
そして3つの素材の中では最も硬度が低く(※理論上)、張りが無く粘りが強いので巻き込みや穂先絡みの負荷に強い、というのが大きな特徴。
なので、非常に細い穂先の材料としてはとても適しています。
しかし、金属が故に一ヶ所に負荷が集中する状態が繰り返し発生し続けると簡単にポロっと折れる金属疲労が起きるというのが難点でもあります。
穂先折れの原因は大きく2つ
材料毎に特徴を挙げてみましたが、お気づきの通り共通する事がひとつあります。
そう、それは
一ヶ所に強い負荷が掛かる、若しくは掛かり続けると、どんな素材の穂先もいずれは折れる
と言うこと。
つまり、穂先の破損はそのロッドの初期不良や設計上の不備がある場合を除き、基本的には材料の強度を越える負荷を一点に掛けてしまった結果として発生するもの。
そんな無理な負荷を発生させてしまう状況は大きくは2つあります。
1.巻き込みや穂先絡みによる破損
ひとつ目に挙げるのはまず巻き込みと穂先絡み。
- サルカンなどの接続金具をトップガイドに勢いよく接触させてしまうことで鋭角に力が働き一点に負荷が集中 ⇒ 破壊
- 穂先にラインが絡まったことに気付かず次のキャストや投入をして一点に負荷が集中 ⇒ イチコロ
言わずと知れた穂先破損の定番ミスで、これが起こるのは完全にアングラーの不注意、つまり”事故”です。
巻き込みはよそ見をしながら巻いてしまうことで起こりますし、穂先絡みは確認不足でしょう。
まぁ、ある程度の太さのある穂先であれば、簡単には折れない場合も多いのですが、非常に繊細な穂先を持ったロッドでは致命的になりますのでよそ見厳禁、確認励行!!
ちなみにですが、マルイカの本格的なゼロテン穂先を使用している場合には、リーダーの結節部分が小口径のガイドを通らずに破損する事故も多いです。
これについては以前に記事を載せましたので参考ください。
参考 : 動画で見る “本格ゼロテンロッド向け” リーダーの結び方
2.事故以外での破損
二つ目は ”事故” 以外の原因です。
そして、今回の記事で特にお伝えしたかったのがこちらの問題。
「巻き込みや穂先絡みを起こしていないのに、なぜか気づくと穂先が折れている。しかも何度も似たようなことが起こる」
穂先を折ろうと思う人なんてひとりもいないはずなのに、何故か良く折る人は決まっていて、これを、「繊細な穂先の竿を使っているから仕方ないんだ」と諦めてしまっている方もいます。
しかし、折らない人は全くと言っていいほど折らないというのも事実。
つまり、頻繁に折る人には何か原因があるわけです。
原因がある以上それを改善することも可能なはずですから、諦めずに前向きにいきましょう。
穂先は折れるんじゃない!折ってるんだ!!
釣りの最中に穂先折れが起こるのは、先に触れた通り『穂先を鋭角に曲げた状態で強い負荷を掛ける』状態が発生しているからです。
事故は起こしていないのに気づいたら穂先が折れていた、という場合においても、結局物理的な原因は同じです。
しかも何度も繰り返し発生するとなれば、釣りをしている際の一連の動作のどこかで穂先折れの原因を作っているのは明白。
言ってみれば「折り癖」です。
いや、別に犯人捜しをして問い詰めたいわけではなく(笑) 論理的に考えると原因はロッドの操作方法にあるという事が言いたいのです。
つまり、
穂先を良く折る = 折ってしまうような負荷の掛け方を一連の動作の中で無意識にしてしまっている
という結論になります。
破損は2つの要因の組み合わせで起こる
実際に手元にある穂先で試してみると分かりますが、鋭角であってもゆっくりと曲げていくだけでは意外と折れません(限界はありますが)。
また、釣りでは急激に強い負荷が掛かるというのは普通に発生する状態ですから、これだけで折れていてはロッドとしての機能は果たせません。
つまり、これら二つの要素が同時に発生することが破損に繋がるわけです。
鋭角に曲げる + 急激に強い負荷を掛ける = 折れる
このメカニズムを元に、両方が揃わないようにしていくことが出来れば折り癖は解消できそうですよね。
破損する場面はいつか?
因みに、どのような場面で穂先折れが発生しやすいのかというと、
- アワセ(空アワセ含む)やしゃくり
- 仕掛けの回収時や魚の取り込み、再投入時
となります。
どちらも船釣りのアングラーが必ず行っている基本動作なのに、折る人と折らない人が存在する。
となれば、これらの動作の中で前述の2つの要因(鋭角に曲げて、且つ急激に強い負荷を掛ける)を作ってしまっている人が折り癖のある人という事になります。
アワセ、しゃくり等の誘い、仕掛けの回収、魚の取り込みに共通するのは「竿を立てる」動作で、これで穂先とラインの角度は鋭角になり一つ目の条件が揃います。
この状態から
- 更なる強いアワセやしゃくり
- 重い錘や魚がついている仕掛けをぶら下げる
と二つ目の条件が揃うとビンゴです。
穂先を折らない為の具体策
ここまでは、穂先は2つの要因が重なることで折れると言う事をお伝えしてきました。
で、ここからは実際に「折り癖」に悩んでいる人がすべきことをお話していきます。
穂先とラインの角度を徹底的に意識する
しつこい様ですが、「折り癖」のある人は動作に原因がありますから、まずは穂先とラインの角度を極端に鋭角にしない癖をつけることが先決です。
それには
- 穂先とラインの角度を良く見る意識を持つこと
- 良く見える様に構えること
- 良く見える様に偏向グラスなどを利用すること
が第一です。
穂先とラインの角度については以前の記事でも触れたので併せて確認してください。
参考 : 釣果が安定しない人必見!!基礎固めでこっそり上達!?
参考 : マルイカ ゼロテン釣法でお悩みの方必見!!アタリを大きく出す方法
アワセやしゃくりの動作時には比較的冷静に穂先を見ることが出来ると思います。
穂先を鋭角にした状態から力任せに追いアワセを入れたり、突き上げるようなアワセを入れる等はもってのほかですが、意外にやってしまう人は多いです。
おそらく穂先を見ていないか、角度についての意識が低すぎるのが原因ですから、上記の対策が出来れば改善していくと思います。
自分の動作がどうなっているかわからないという人は、誰かに頼んで釣り姿を動画に撮って貰うのも超オススメです。
取り込み動作の改善
「折り癖」に悩む人の多くが、取り込みや仕掛けの回収時に不適切な角度で穂先を曲げています。
魚が掛かっていると焦ってロッドを思いっきり立てて取り込んでしまう人を良く見ますが、正直言ってあれはかなりヒヤヒヤものです。

持ち上げた魚や仕掛けをスパッと手で捕まえられれば、その後に無理な負荷が乗ってこないのでセーフですが、うまくキャッチできなかったり魚に暴れられて落としてしまったりすると急激な負荷が発生します。
そして、そもそも穂先に対する意識が低いと「気が付いたら折れてた」ってなっちゃいます。
特に極先調子のカワハギや湾フグロッドであれば、一気に破損のリスクが高まりますし、実際にこれらの釣り物では「折り癖」のある人がかなり存在します。
これを解消する方法が次の画像のように、竿先を立てずにパーミングした手を肩から後ろへ引く方法です。

穂先を鋭角に曲げずに取り込むことが出来るので、急激な負荷が掛かっても折る心配がありません。
参考動画 : 【カワハギ釣り】穂先折れ回避術!!ロッド破損を劇的に減らす四つの方法とは??
私はこの方法で取り込みを行っているので、湾フグにさんざんのめり込んでいた当時も穂先を一度も折らずに済んでいますし、カワハギでは、穂先絡みに気付かずにキャストしてしまった時と、長く使い続けた穂先の素材疲労によるものの2本に留まっていて、非常に有効なのがお分かりいただけると思います。
取り込み後に気をつけること
竿やすめなどを使って船べりにロッドを立てかけている時、実は結構危険な状態にあると言えます。
というのも、この時の穂先とラインの角度は鋭角の状態になっているからです。

この状態で不用意に引っ張ってしまう。
例えば針から外そうとした魚が暴れたり、錘が転がり落ちたり、針をウエアのどこかに引っ掛けて引っ張ってしまったり・・・・そして穂先を見たら折れていた、というお話をとてもたくさん聞きます。
とはいえ、このような不注意や事故があっても折らない人は折らない。
その秘密はとても単純で「リールのクラッチを切る」ことにあります。
不用意に引っ張っても糸が出ていくので穂先へダメージが伝わらないわけですね。
具体的には、魚を取り込んでロッドを置く際にクラッチを切っておくんですが、これを習慣にしている人はこのような破損とは無縁です。
仕掛けの再投入時にすべきこと
もうひとつ、具体的に習慣付けておくことで劇的に破損を減らせる方法があります。
それが再投入時の穂先絡みの確認です。
この確認について最近気が付いたのですが、ざっと目で見るだけで確認完了としている人が多いようです。
しかしこの目で見るだけというのが結構くせ者です。
取り込み後の穂先とミチイトとの関係は鋭角になりやすいというのは先程も言及しましたが、これは言い換えればミチイトが穂先に纏わりつきやすい状態といえます。
しかも結構な鋭角ですから、ざっくり目で見た程度では、トップガイド直下くらいに絡んだラインは見えない場合が多い。
それをそのまま投入してしまうと穂先にダメージがいってしまうので「気が付くと折れていた」となるわけですね。
これを確実に回避するにはどうしたら良いのか?
それは、投入時に仕掛けを持って引っ張ってミチイトを張り、リールのクラッチを切ってほんの数センチで良いのでミチイトを出してやること。
ちょっとでも穂先に絡んでいればスムーズにミチイトが出ていきませんからすぐに分かります。
特にカワハギ、マルイカ、湾フグなどの繊細な穂先を使用する釣りをする方は、この確認動作は絶対に習慣にしましょう。
一気に破損が減るはずです。
まとめ
小物釣りのロッドは年々進化して繊細な穂先を搭載するようになってきており、今後もこのような傾向は続いていくと思います。
冒頭にも書きましたが、私の仕事としては穂先のご注文をいただくのは大歓迎ですが、折れた穂先を見るのは非常に辛く出来れば折ってほしくないと考えて今回の記事を書くことにしました。
なぜが安全な取り込み方法についても、具体的策が殆ど示されてこなかったように思いますので、是非ご参考いただければと思います。
材料の開発でめちゃくちゃな扱いをしても一切折れない!!なんて夢の穂先ができれば最高なんですがね(笑)
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お知らせ2025年6月20日釣りビジョン「F JUNCTION」出演
お知らせ2025年6月20日釣りビジョン「F JUNCTION」出演 WEBレッスン2025年4月30日【シロギス釣り】胴突き仕掛けをフル活用!! 〜東京湾西側流の釣りを紐解く〜
WEBレッスン2025年4月30日【シロギス釣り】胴突き仕掛けをフル活用!! 〜東京湾西側流の釣りを紐解く〜 LTアジ2025年4月29日「攻めのライトアジ教室」開催します
LTアジ2025年4月29日「攻めのライトアジ教室」開催します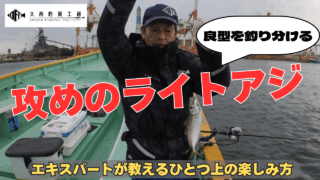 LTアジ2025年4月26日【ライトアジ新作動画】〜サイズの釣り分けとライン引きのバリエーション〜 を公開しました
LTアジ2025年4月26日【ライトアジ新作動画】〜サイズの釣り分けとライン引きのバリエーション〜 を公開しました


